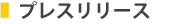年商300億円 角上魚類の比類なき戦術
2016年12月27日
魚屋が次々と廃業に追い込まれる中、角上魚類は創業以来40年以上も右肩上がりの成長を続けている。日本人の魚離れの余波をものともしない躍進は現代の奇跡と言っていいだろう。インタビューからは、日本文化特有の、昔にあったお魚屋の原型を再現したに過ぎないことが窺える。そうは言っても誰にでも真似のできる技ではない。底流には栁下流の比類なき発想が埋もれている。新潟市在住のライター・石坂智恵美氏がこのほど、角上魚類の成功ノウハウを詰め込んだ「魚屋の基本」を上梓したことで、石坂氏にもご登場願った。(聞き手、本誌編集長・瀬戸田鎮郎。一部敬称略)。
栁下浩三社長は角上魚類の前身、魚卸を営む角網の次男坊として生を受けた。昭和40年代に入るとスーパーの台頭で卸先の魚屋が次々と姿を消していった。取引先の減少は栁下を粛然とさせた。跡目を継ぐことにしていた栁下の心は曇った。
スーパーを見て回ると、目は活々と光り、瞬時に顔つきが変わった。重大な想念が閃いた時に人がよくする凝固とした表情になっていた。
「値が高い、これだば俺でもやれる」。時代の波に乗るスーパーだったが、当時は卸値の2倍以上で売られていたのだ。
問屋から小売りに転換を図った瞬間だった。魚の行商で培った昔ながらの魚屋の原風景が角上魚類の原点なのだ。
すべては、そこから始まった。
―魚介類の年間消費量は、平成13年の40キログラムから平成25年27キログラムへと3分の2に減少。その要因として、昭和30年代から40年代にかけて台頭したスーパーにある。多店舗展開を進めるスーパーは、どうしても効率重視にならざるを得なかった。一定の漁獲量が見込め、無難に売れるサバやサケ、イワシなどを重点的に売っていった。大量販売が命題なので、魚の旬に無頓着になっていった。消費者ではなく、店の都合を優先し、ロスの少ない売り方をするようになり、美味しい魚を伝えることをしてこなかった。美味しくても売れ筋から外れた魚を、売る工夫をする余裕も時間もスーパーにはなかった。
石坂さんは著書でこう記されています。スーパーが台頭したことで魚離れが進んだというのは面白い着眼です。
栁下社長(以下、栁下)「スーパーは、アメリカから渡ってきた商売の形態です。日本ではそれまで、お客様の要望によって、その場で魚を切ったり焼いたりして売っていました。魚は、ほぼ毎日、売れ残りやロスが出ます。ロスを出さない商売をするのがスーパー。スーパーが台頭することで魚の売り方が変わってしまった。
ロスを出さない商売に魚が組み込まれたので、旬の魚、美味しい魚をお客様に食べていただくという魚文化が消えていったわけです。だから、都会の人、海のない地域の人は、魚は『味の決まった切り身しかない』、『いつ買っても同じものしかない』と思って、魚を食べるという昔からの文化を忘れてしまったと思うのです。
親が魚を食べなければ、子供も当然、魚を食べません。子供は魚の味を知らないままに大きくなる。それが繰り返されて20年、30年続いてきたんですね」
石坂氏(以下、石坂)「私の実家は肉屋でした。スーパーの台頭によって、店じまいを余儀なくされました。いまの栁下社長のお話はリアルに分かります」
魚は面倒な商材
栁下「肉は解体しないと一般には売れませんので、スーパーになっても売り方だけは変わりませんでした。安く大量に仕入れられるかどうかだけです。
魚屋は魚を、『今日はイワシのイキがいいよ』、『ハタハタはこういう食べ方をすると美味しいよ』、『今の旬はアジだよ』などとお客様にアピールして売ってきたわけです。
ですが、スーパーは生魚そのものを店頭に並べなかった。…続きは本誌に