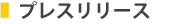田中角栄と柏崎刈羽原発誕生秘話
2015年07月27日
柏崎市と刈羽村の両議会が先月、東京電力柏崎刈羽原発の早期再稼働を求める請願を賛成多数で採択した。誘致から45年が経過した同原発の歴史の裏側に迫る。
角栄王国のキーマン
東京電力柏崎刈羽原発の誘致が決定されたのは昭和44年9月のことである。当時、柏崎市長を務める小林治助の下で、原発誘致に力を尽くした長野茂・市長公室長に、原子力般の知識・情報を提供したのは、日本原子力研究所環境放射能課の亀田和久課長代理である。その亀田の部下として、当時、原子力発電の啓発活動に奔走した誠心会第2期生の追田吾郎(東京都在住、79)は、「柏崎刈羽原発の誘致を働きかけたのは理研ピストンリング工業会長で、東電顧問の松根宗一氏。その松根氏と田中角栄元総理は、ともに理化学研究所第三代所長の大河内正敏子爵を恩師と仰ぐ仲で、この二人の存在がなかったら、柏崎刈羽地域への原発誘致は実現しなかったでしょう。そして、それを具体化へと導いた司令塔は東電一の切れ者といわれた筆頭常務の小松甚太郎氏。この小松常務を取り巻くように、角栄王国のキーマンが配置されていました。そのキーマンとは、松根宗一、小林治助、亘四郎(新潟県知事)、祢津文雄(新潟県議)、木村博保(刈羽村長、県議)の5人でした」と話す。
前出の長野氏によれば、小林治助が「原子力発電」という聞きなれない言葉を耳にしたのは助役時代の昭和36年のことだったという。そのきっかけは日本石油の柏崎製油所をめぐる存廃問題だった。
柏崎は石油の町として栄えてきた。ところが、昭和30年代に入ると、明治以来の柏崎製油所は時代遅れの老朽プラントとして凋落の一途を辿る。そこに追い討ちをかけたのが、原油をガソリンや灯油などに分留する際に残る「C重油」といわれるものだった。このC重油は現在も船舶用の大型ディーゼルエンジンや火力発電所などの燃料に使われる。だが、当時の柏崎の地域産業にC重油を消費するだけの体力はなかった。それほど柏崎経済界の地盤沈下は深刻で、現在、ジリ貧といわれる柏崎経済界の状態と酷似している。このままでは柏崎製油所は閉鎖に追い込まれる。そこで浮上したのがC重油を大量に使う火力発電所の誘致計画で、昭和36年、柏崎市助役の地位にあった小林治助は、市長の吉浦栄一とともに、東北電力新潟支店に出かけた。ところが、取締役支店長の館内一郎は「これからは火力発電の時代ではなく、原子力発電が主流になる時代です。柏崎では原子力発電をお考えになったらいかがですか」といった。その時は、治助も吉浦市長も、館内の言葉を逃げ口上と受け取り、原子力発電など一顧だにしなかった。
ところが、治助が市長に就任した昭和38年、事態は急変する。治助が初当選と市長就任のあいさつのため、松根宗一に面会したとき、柏崎で原子力発電所の建設を検討するよう強く勧められたのである。
その4年後、事態は前に動いた。県が原発立地の調査地点を荒浜に決め、翌43年、通産省の委託を受けた県の地質調査が開始されたのである。
泥にまみれた砂丘地
その少し前、小林治助は目白の田中邸を訪問している。正確な年月日は明らかではないが、「荒浜での原発建設計画が表に出る少し前、ちょうど柏崎市議会に原発誘致のための研究委員会が立ち上がる少し前の話なんですが、父は単身、東京の目白邸に乗り込んで田中先生にクギを刺しているんです」と治助の長男の正明は証言する(講談社刊『田中角栄と消えた闇ガネ』より)。
当時、角栄は、佐藤内閣を揺るがせた一連の「黒い霧」の責任を取る形で辞任していた自民党幹事長に返り咲き、後の『日本列島改造論』の原典となる「都市政策大綱」をまとめていた時期である。…続きは本誌にて