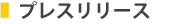新潟駅を中心とした南北軸に基幹的公共交通が必要だ!
2025年03月27日
 新潟市の元政策監統括であって都市交通政策課長も歴任した松田暢夫氏は、日本都市計画学会に所属しながら「考える会」の副代表を務める。都心軸と公共交通について他市の事例を挙げながら、新潟市の公共交通と都心軸の現状を考察。今後の展望と課題解決に向けた考え方を述べた。
新潟市の元政策監統括であって都市交通政策課長も歴任した松田暢夫氏は、日本都市計画学会に所属しながら「考える会」の副代表を務める。都心軸と公共交通について他市の事例を挙げながら、新潟市の公共交通と都心軸の現状を考察。今後の展望と課題解決に向けた考え方を述べた。
都市軸に必要な基幹的公共交通
1990年に年間利用者数が延べ690万人いた新潟交通のバス利用者は、30年間で3分の1程度にまで減りました。
新潟市の移動手段の変化を見ますと、2014年のマイカー利用率は69・6%、2022年は72%と微増しましたが、この数値は政令市の中でトップクラスの高さ。マイカー依存度の高い新潟市と言えます。この間、バスの利用率は連接バスの導入もあって少しだけ増えた時期がありましたが、頭打ちでいままた減少傾向にあります。
マイカー利用率が高い新潟市はCO2発生量が政令市ワースト1です。利用率がなかなか上がらないバスは、ドライバーの数の減少にも頭を悩ませています。タクシーも同様です。
さて、大都市にはだいたい都心軸(都市軸)というものがあります。人間にたとえると背骨です。拠点を結んだり軸沿いに都市機能が集積したりしています。
そして、ここが大事なのですが、基幹的公共交通の軸が形成されています。一例を挙げると、富山市にはLRTやライトレールといった路面電車が、金沢市にはバスが、宇都宮市にはLRTが、北九州市・小倉にはモノレールが公共交通の軸として機能しています。
合併していまの姿を形成している新潟市には、4つの都市軸があります。1中央区―西区―西蒲区、2中央区―南区、3中央区―江南区―秋葉区、4中
央区―東区―北区です。新潟市中心部を見ると、市が政策的に推進している新たな都市軸の「にいがた2㎞」がありますが、これら都市軸に基幹的公共交通の軸が形成されていると言えるでしょうか?
「にいがた2㎞」を延伸させて新たな都市軸、そして基幹的公共交通の軸が計画されています。1つは市役所や大学病院などを結ぶ白山地区への延伸、
1つは文教施設やスポーツ施設があり、大型商業施設の進出が予定されている鳥屋野潟南部への延伸です。
この新たな軸を地図に落とし込むと、軸の沿線に商業施設、シティホテル、文化・交流・スポーツ施設、教育施設、病院、市(区)役所が圧倒的に集中していることが分かるんですね。これを仮に「南北軸」とすると、南北軸の強化は将来に向けて必要だなと思うのです。その理由について5点ほど記しておきました(図表1参照)。
なお、南北軸の途中にJR新潟駅があります。駅の高架下をバスが往来できるようになりました。ところが、全便が南北直通していない。いろんな施設が南北軸の沿線にあるということは、言い換えるとアクセスがしやすいということであって、すなわち「儲けることができる」と言えるわけです。それなのに、必ずしも直通で往来できるわけではないという現状は、儲けること、アクセスの利便性の観点からも考えないといけないと思います。…続きは本誌で